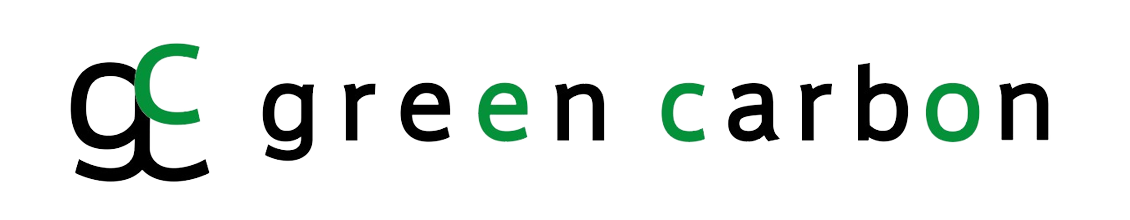東南アジアでのNature-Based ソリューションにおける私の役割
氏名: アヌロッド・バル・タマン
職位: アナリスト/プロジェクト・オペレーション、海外事業部
専門分野/担当業務: タイ・カンボジアにおけるAWDプロジェクト・オペレーション・リード
Green Carbon入社理由: サステナブルなコミュニティ開発への強いコミットメントに駆られてGreen Carbonに入社しました。旅行業界から転身して国際協力の修士号を取得した後、東南アジアの脆弱なコミュニティと直接関わる有意義な機会を求めていたところ、発展途上国で自然由来のビジネスを創出するというGreen Carbonの使命と、そのダイナミックなスタートアップ環境は、私の個人の特性やキャリア志向とも深く共鳴したんです。
経歴: 旅行・観光産業で5年間働き、主に東京2020オリンピック・パラリンピック大会までスポーツマーケティング部門に従事していました。加えて、前職ではアジア太平洋地域に焦点を当てた様々なマーケティングポジションも経験しています。
専攻/学歴: ホスピタリティ・ツーリズム専攻(学部)、国際協力政策専攻(大学院)
趣味/休日の過ごし方: ハイキング、料理、スポーツ観戦
SNS: www.linkedin.com/in/anurodh-bal-tamang-0a6344222


Q. 簡単な自己紹介と、これまでのキャリアについて教えてください。
こんにちは、バルと申します。ネパールというとても綺麗な国の出身です。学部・大学院ともに大分の立命館アジア太平洋大学で学びました。大学院では、安全で強靭かつ持続可能な観光コミュニティの構築をテーマに研究を行いました。
現在はGreen Carbonでプロジェクト・オペレーション・アナリストとして働いており、カーボンクレジット事業の一環として、タイとカンボジアでのAWD(灌漑技術)プロジェクトの実施を監督しています。
Green Carbonに入社し大学院に進学する前は、旅行・ホスピタリティ業界で数年間働いていました。東京2020オリンピック・パラリンピック大会を含む大規模な国際イベントの物流・ホスピタリティプロジェクトを管理したり、前職のアジア太平洋本社でグローバルインバウンド部門のデジタルブランディングやメディア戦略を担当したりしていました。
Q. どのような仕事に携わっていますか?役割について詳しく教えてください。
プロジェクトのオペレーションをリードする立場として、私の役割は多岐にわたります。現地チーム、ステークホルダー、政府機関、パートナー大学と密接に連携し、プロジェクトが適切なタイミングで、かつ技術的・方法論的基準に沿って実施されるよう努めています。
予算計画と交渉、データモニタリング(水位、ガス排出量、農業実践、土壌サンプリングなど)、そして認証プロセスに必要なプロジェクト文書の準備調整といった重要な機能もサポートしています。
現場でのオペレーションに加えて、私たちのチームは内部プロセスの強化においても重要な役割を担っています。これには、オペレーションマニュアルやオンボーディングガイドの開発、さらにはスタッフの能力向上を図る研修セッションの企画なども含まれます。
Q. 現在の仕事を志すきっかけは何だったのでしょうか?
持続可能性分野への関心は、私がネパールで育った経験に根ざしています。そこで気候変動や自然災害を間近で目の当たりにしたからです。そのため、以前は旅行会社で働いていたものの、COVID-19パンデミックをきっかけに持続可能なコミュニティ開発のために何ができるかを考えるようになりました。これが国際協力・政策の修士号取得につながったんです。卒業後は、おそらくは開発コンサルタントとして、開発セクターで働くことを志していました。
そうした方向性の企業を調べているうちに、Green Carbonを見つけました。なぜここで働きたいと思ったか?
魅力だったのは、スタートアップとしてこのようなサステナビリティ推進セクターに挑戦し、自然由来のソリューションビジネスを構築することで積極的な環境インパクトを創出しようとする姿勢でした。私にとって特に重要だったのは、東南アジアの脆弱なコミュニティや農家のために何かしたい、彼らと直接関わりたいという想いだったため、そうした想いに応えられる場所としてGreen Carbonを選んだんです。
さらに、私の家族は農業関連の事業を営んでおり、新鮮な野菜や果物のサプライチェーンをより持続可能にし、食品ロスを削減する取り組みを行っています。そのような背景もあって、この会社のビジョンと、自然の力を通じて積極的なインパクトを創出したいという私たち自身の志向との間に、何か通ずるものを強く感じたのです。
Q. 仕事のやりがいや、最も充実感を感じる瞬間について教えてください。
私が最もやりがいを感じるのは、技術的なことや文化的なことも、常に学び続けられることです。カーボンクレジットへの理解を深めるだけでなく、伝統的な農業実践や水田生態系の複雑な仕組みについても貴重な洞察を得ることができました。現地のステークホルダーと関わることで、農業業界における多様な文化的視点についても学べています。彼らが直面している課題を理解し、それらをどう解決できるかを批判的に考えることは、私の大きなモチベーションの源になっています。
また、職務の初期段階から重要な責任を託されていることも充実感につながっています。新しく、異なる背景から来た私にも関わらず、国をまたいだオペレーションを管理する機会をいただけたことは、謙虚な気持ちと同時に大きな刺激にもなりました。この信頼が、私を学び続け、向上し続けるよう駆り立てています。カンボジアとタイにまたがる非常に技術的なプロジェクトの管理には課題も伴いますが、同時に成長し、適応し、持続可能な発展に意義深い貢献をする貴重な機会でもあります。
Q. これまでにどのような課題に直面しましたか?
現在、カンボジアとタイ両国でのオペレーション管理において私が直面している主要な課題の一つは、働く文化の違い、関係者間の複雑な力関係、そしてカーボンクレジットの方法論の適応をナビゲートしていくことです。各国がそれぞれ独自の文脈を持っており、高度な適応力と細やかな理解が求められます。
まだこの役割に就いて日が浅いので、私たちのオペレーションに関わる技術的・方法論的詳細についてより深い理解を築いている最中です。時には、明確な答えや方向性が不足していることがあり、特に迅速で正確な判断が必要な場面では落胆することもあります。しかし、これを挫折ではなく、成長のための貴重な機会と捉えるよう心がけています。このおかげで、同僚やパートナーとより積極的に関わり、より多く読み、より良い質問をし、理解を継続的に研ぎ澄ませて、より頼もしいと思ってもらえるリーダーシップを発揮できるようにと、自分を追い込むことができています。
Q. 10年後の自分をどう思い描いていますか?また、挑戦してみたい課題はありますか?
個人的には、あまり先のことを考えるタイプではありません。ただ、もし今後10年を思い描くとすれば、持続可能な社会発展に関わる分野で、特に政策立案への関与を通じて、より広範囲にインパクトを与えられるポジションにいたいと思います。地域のニーズとグローバルな持続可能性目標を橋渡しし、環境と社会の両方の課題に取り組む包括的でコミュニティベースのソリューションの設計を支援するといった挑戦に意欲を感じています。
また、私たちのオペレーションをアジア以外にも拡大する可能性についても挑戦してみたいとワクワクしています。東南アジアで学んだ教訓を新しい地域に適用し、同時に異なる環境・文化・規制の文脈に適応させるといったこと——是非してみたい挑戦です。加えて、長期的な志向の一つとして、日本と私の祖国であるネパールを結ぶ取り組みに貢献したいと考えています。ネパールは政治的複雑さを抱える小さな国ですが、特に自然由来のソリューションやカーボンクレジット開発などの分野で、意義深い協力関係を築けると、私は考えています。