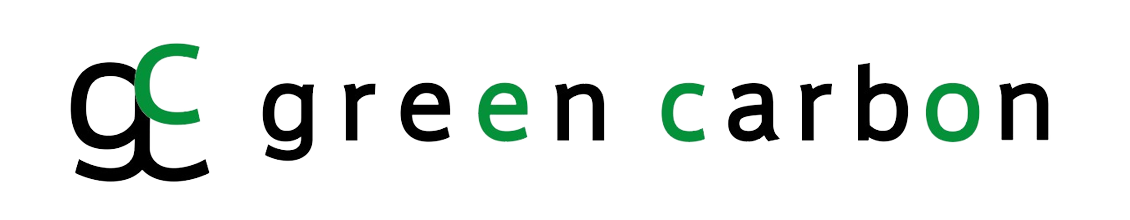今回は、タイのローカルマネージャとして活躍するパラマ・ブンクーンさんにインタビューを行いました。多様なバックグラウンドを活かし、活躍しているパラマさんが日々どのような業務をしているのか、ぜひ最後までご一読ください!
氏名:パラマ・ブンクーン
所属部署・役職:ローカルマネージャー(タイ)
専門分野/担当業務:水田におけるAWD(間断灌漑)とバイオ炭プロジェクト、ステークホルダーエンゲージメント、カーボンクレジット研究、地域連携の調整、プロジェクト実施
ジョインしたきっかけ:多分野にわたる自身の経験を活かし、協調的かつ地域に基づいたアプローチを通じて、目に見える環境的・社会的影響を生み出すため。
これまでの経歴:カーボンクレジット研究、議会助言、都市部の難民教育を中心とした非営利・国際協力のリーダーシップ経験。
専攻/学んでいたこと:コンピューターサイエンス理学士、コンピューターサイエンス理学修士、教職教育課程修了証、教育経営学教育学博士
趣味/休日の過ごし方:文化史跡を巡る旅行、公共政策とイノベーションについての本の読書


Q. これまでのキャリアを含め簡単な自己紹介をお願いします。
私はパラマ・ブンクーンと申します。教育、テクノロジー、そして地域社会との連携を軸に、学際的なキャリアを歩んできました。この10年ほどは、カーボンクレジットの研究をはじめ、タイの国会委員会での政策アドバイザー、大学の副学長といったポジションも経験しました。
また、UNHCRのプログラムで、都市部に暮らす難民の子どもたちへの教育支援を行う非営利団体の運営にも深く関わりました。もともとコンピュータサイエンスと教育行政を専門にしていたこともあり、複雑な仕組みの中でも、常に「人」を中心に考える姿勢を大切にしています。
Q. どのような仕事に携わっていますか?業務内容をお聞かせください。
現在は、Green Carbonのタイ現地マネージャーとして、主にAWD(水管理技術)やバイオ炭プロジェクトの現地での実施を担当しています。具体的に、地域の方々との関係構築や能力強化、現地ステークホルダーとの調整を行いながら、カーボンクレジットの認証に必要な調査・レポート作成にも関わっています。
日々、農家の方々や地域の教育機関、行政との連携を大切にしながら、プロジェクトの目的と現地ニーズがしっかりと合致するよう心がけています。また、持続可能で地域に根ざした取り組みになるよう、現場目線を大切にしています。

Q. Green Carbonで働こうと思ったきっかけは何ですか?
この仕事に惹かれた理由は、これまで取り組んできたカーボンクレジットの研究と、地域社会での実践的な開発活動の両方に関われる点でした。Green Carbonでは、環境科学の知見を現場レベルで活かせるユニークな機会だと感じました。
また、地域の農家の方々との協働から、国レベルの政策議論まで、さまざまなレイヤーで仕事ができるのも魅力です。まさに、これまでの経験や関心が活かせるポジションだと思っています。
Q. Green Carbonでのやりがいは何ですか?
地域の人たちが「知識」と「機会」の両方を得て、少しずつ変化していく様子を間近で見られることに、大きなやりがいを感じます。たとえば、節水の技術が役に立ったと話してくれる農家の方や、「気候変動への解決に関われて誇りに思う」と話す地域のパートナーの姿を見ると、人を中心にした持続可能な変化は本当に可能なんだと実感しました。
また、気候変動という地球規模の課題と、地域の暮らしや生計をつなぐ現場で働けるのも、この仕事の魅力のひとつです。将来的に、地域の方々がより安定的で持続可能な収入を得られるチャンスが広がっていくのを見ると、とても励まされます。

Q. 今までに直面した課題は何ですか?
課題のひとつは、国際的なパートナーや地域コミュニティ、行政機関といったさまざまな関係者の期待や考え方の違いを調整し、まとめていくことです。私の役割は、それぞれの立場の間に立ち、うまく折り合いをつけ、共通のゴールを描くことが求められます。もうひとつの難しさは、不確実性の中でプロジェクトを進めていくことだと思います。
Q.10年後のご自身の姿と、今後取り組んでいきたい課題について教えてください。
10年後には、環境のレジリエンス(回復力)と、誰も取り残さない教育、地域のエンパワーメントを組み合わせた取り組みを、タイ国内やアジア地域で主導したり、支援していたいと考えています。特に、テクノロジーやデータ、教育を活用して、気候変動の影響を受けやすい立場にある人々をどう支援できるか興味を持っています。また同時に、誰も取り残さず、説明責任を果たし、地域が主体となったまま拡張できるモデルを構築することが課題であるとも考えています。